
はじめに
2025年10月、自民党の高市早苗総裁が新首相に就任し、長引く物価高への対応として大規模な補正予算編成に着手する方針を明らかにした。臨時国会で審議される見通しの補正予算は、国民生活を直撃する物価高への緊急対策から成長投資まで幅広い施策を含む包括的なパッケージとなる見込みだ。
補正予算の全体像
予算規模と基本方針
高市政権が準備する補正予算は、以下の基本方針に基づいて編成される:
- 財源確保:税収の上振れ分や基金残高を活用し、赤字国債に依存しない財政運営
- 即効性重視:物価高に苦しむ国民への迅速な支援
- 成長投資:中長期的な経済成長を見据えた戦略的投資
想定される予算規模
| 項目 | 規模 | 備考 |
|---|---|---|
| 低所得者向け給付金 | 0.8〜1.5兆円 | 住民税非課税世帯・低所得年金生活者向け |
| 診療・介護報酬引き上げ | 数千億円規模 | 医療・介護従事者の処遇改善 |
| 地方交付金の積み増し | 未定 | 自治体の物価高対策支援 |
| エネルギー対策 | 継続中 | ガソリン補助・電気料金支援 |
主要施策の詳細
1. 物価高対策(緊急支援)
現金給付制度
対象者と給付額
| 対象世帯 | 給付額 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 3〜5万円 | 2025年度内 |
| 低所得年金生活者 | 3〜5万円 | 2025年度内 |
| 全国民一律給付 | (見送り) | 石破前政権の公約から転換 |
ポイント
- 当初掲げられた「国民一律2万円給付」は事実上白紙化
- 所得制限を導入し、真に支援が必要な層に重点配分
- 総事業費は最大1.5兆円規模を想定
エネルギー価格支援
継続中の支援措置
| 支援内容 | 規模 | 実施期間 |
|---|---|---|
| ガソリン補助 | 10円/リットル | 継続中(基金活用) |
| 電気・ガス料金支援 | 実施済み | 2025年9月使用分で終了 |
新たな施策
- ガソリン税暫定税率の廃止を臨時国会に法案提出
- 施行までの間は基金を活用した価格引き下げを継続
2. 医療・介護分野への支援
診療・介護報酬の引き上げ
背景
- 医療・介護従事者の慢性的な人手不足
- 物価高による経営環境の悪化
- 従事者の処遇改善による人材確保の必要性
期待される効果
- 医療・介護サービスの質の維持・向上
- 従事者の賃金上昇による消費拡大
- 地域医療・介護体制の安定化
3. 地方自治体支援
重点支援交付金の拡充
目的
- 地域の実情に応じた柔軟な物価高対策の実施
- 自治体の財政基盤強化
- 地域経済の活性化
活用例
- 地域独自の生活困窮者支援
- 中小企業への経営支援
- 公共施設の光熱費増加への対応
4. 給付付き税額控除の導入検討
制度概要
特徴
- 所得税額から直接控除
- 控除額が所得税額を上回る場合は現金給付
- 中低所得者の実質的な税負担軽減
スケジュール
- 党内での議論を開始
- 具体的な制度設計は今後の検討課題
2026年度予算への影響
概算要求の状況
全体規模
| 年度 | 一般会計概算要求額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 122兆円台 | 過去最大 |
| 2025年度 | 約114兆円 | – |
主要経費の内訳
国債費
| 項目 | 金額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 国債費 | 28.9兆円 | +7.0% |
| 想定金利 | 2.1% | +0.2ポイント |
増加要因
- 日銀の利上げによる金利負担増
- 既発債の借り換えコスト上昇
防衛費
| 年度 | 防衛費 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2026年度要求 | 8.5兆円 | +7.4% |
背景
- 2023〜2027年度の5年間で総額43兆円の防衛費増額計画
- 安全保障環境の厳しさを踏まえた継続的な増強
社会保障費
| 項目 | 見込み額 |
|---|---|
| 自然増 | 4,100億円 |
課題
- 少子化対策の財源確保
- 医療・介護費用の効率化
- 持続可能な社会保障制度の構築
財政健全化との両立
プライマリーバランス(PB)目標
2025年度目標
- PB黒字化を目指す
- ただし、達成の不確実性は高い
課題
- 補正予算による歳出増加
- 税収の持続性への懸念
- 金利上昇による国債費の増加
財務省の懸念
指摘されているリスク
- 財政規律の緩み
- 大規模補正予算の恒常化
- 当初予算の弾力性喪失
- 市場の信認低下
- 長期金利の上昇リスク
- 円安による物価高の加速
- 持続可能性への疑問
- 社会保障費の自然増
- 防衛費の継続的増加
野党との連立協議
日本維新の会との連立
合意の可能性
- 2025年10月20日に政策協議実施
- 21日の臨時国会で首相指名の見通し
政策面での影響
- 物価高対策の具体化
- 規制改革の推進
- 財政健全化への配慮
国民民主党との協力
想定される政策の増幅
- より積極的な財政出動
- 金融緩和継続への圧力
- 減税措置の拡大
金融市場への影響予測
株式市場
| 指標 | 予想レンジ | 期間 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 最大49,000円 | 1か月程度 |
上昇要因
- 政府投資拡大への期待
- 各種減税策による経済刺激
- 円安進行の追い風
為替市場
| 通貨ペア | 予想レンジ | 見通し |
|---|---|---|
| ドル円 | 最大155円 | 円安方向 |
円安要因
- 低金利持続への期待
- 積極財政による財政環境悪化懸念
- 「悪い円安」進行のリスク
債券市場
| 指標 | 予想レンジ |
|---|---|
| 10年国債利回り | 最大1.9% |
金利上昇要因
- 積極財政への警戒感
- 超長期ゾーンへの売り圧力
- 財政規律への懸念
専門家の評価と提言
期待される4つの経済政策
- 財政健全化の堅持
- 恒久的な財源の確保
- 大企業への適正な課税
- 歳出の優先順位付け
- 日本銀行の独立性尊重
- 金融政策への政治介入回避
- 中央銀行の中立性維持
- 市場の信認確保
- 成長戦略の明確化
- 投資促進策の具体化
- イノベーション支援
- 生産性向上への取り組み
- 社会保障改革の推進
- 持続可能な制度設計
- 効率化と質の両立
- 世代間公平の実現
リスクと課題
短期的リスク
| リスク | 影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 金利上昇 | 国債費増加、経済への逆風 | 財政規律の維持 |
| 円安加速 | 輸入物価上昇、生活費増 | 為替市場への適切な対応 |
| 市場の信認低下 | 資金調達コスト上昇 | 透明性の高い財政運営 |
中長期的課題
構造的な問題
- 少子高齢化による社会保障費の増加
- 労働人口減少による成長力の低下
- 債務残高の累増
必要な対応
- 歳入・歳出の両面からの改革
- 成長力強化に向けた投資
- 国際競争力の向上
今後のスケジュール
2025年10月〜12月
| 時期 | イベント |
|---|---|
| 10月下旬 | 臨時国会召集 |
| 11月 | 補正予算案の審議開始 |
| 12月 | 補正予算成立(目標) |
2026年以降
- 2026年度当初予算の編成
- 中期財政計画の策定
- 社会保障改革の具体化
まとめ
高市新政権が準備する大規模歳出パッケージは、物価高に苦しむ国民への緊急支援と、中長期的な経済成長の両立を目指す野心的な取り組みである。
主なポイント
- 低所得者を中心とした給付金支給(0.8〜1.5兆円規模)
- 医療・介護分野への重点投資
- エネルギー価格支援の継続
- 給付付き税額控除の検討開始
一方で、財政規律の維持や金融市場への影響など、解決すべき課題も多い。野党との連立協議の行方や、日本銀行との政策協調のあり方が、今後の経済・金融情勢を大きく左右することになるだろう。
新政権には、短期的な支援と長期的な成長の両立、財政健全化への配慮、そして日本銀行の独立性尊重という難しいバランスを取りながら、国民の生活を守り、日本経済の持続的な発展を実現することが求められている。

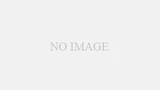
コメント